おじいちゃんの教え
最近、自然災害のニュースが多いですよね……そんな時に、おじいちゃんの言葉を思い出しました。
「最後まで、みんなで分け合わなあかんで」 戦争でひもじい思いをしたおじいちゃんが、私によく言ってた言葉です。子どもの頃は「ふーん」くらいでしたが、大人になってからこの意味がズシンときます。あの頃は笑って聞き流してたけど、今になって、その大事さがじわっと胸にしみるんです。
今の時代も“分け合う力”が必要な理由
令和になった今でも、自然災害は待ってくれません。台風、地震、線状降水帯、大雨被害…ニュースでは「観測史上最強」なんて言葉も珍しくなくなりました。でも、実際に停電や断水が起きたとき、食べ物や水を分けられる余裕を持っている人って、意外と少ないんです。
この前もうちの家のお米が切れそうだったので、いつもお願いしている親戚に頼んだら「ない」ときっぱり言われて…コメ不足だしまぁ仕方ないかと思っていました。。
そしたらたまたまそこの息子さんが来て「お米ちょうだい」って言うたら、あっ…って一瞬なって…また今度…みたいに濁して…(笑)あ、あるんだ…ってそのときハッとしたんですよね。
人間って、自分の分は守りたくなるもの。余分がないと、分けるのはむずかしい。
おじいちゃんの戦争体験
おじいちゃんが「分け合え」と言うのは、ただの優しさやなかったんです。
戦争中、おじいちゃんは遺体を運ぶ役目もしていたそうです。どんなに必死で逃げても助からなかった人たちを、この手で運んだ──その経験から「生き残った人は、最後まで助け合わなあかん」と強く思うようになったと話していました。
職業柄今の年金よりは少しくらいの余裕はあった祖父、お買い物に行けば自分の家だけやなく、うちの母と義弟人家族や近くの妹の家にも必ずお土産。「ひとりで楽しそんだらあかん。戦争で辛い思いしたからな、絶対あかんねん」笑ってそう言いながらも、その目は本気でした。
分け合える備蓄の考え方
備蓄を考えるときは、自分たちにとっても余裕があるように見えるくらいの量を持っておくと安心です。
たとえば家族3人×3日分の水は9Lが目安ですが、そこに+6L(500ml×12本)を加えておくと、気持ちにも余裕が生まれますし、もしものときに誰かに渡すこともできます。
食べ物も同じで、レトルトや乾パンを少し多めに。特に小分けパックや個包装のものは扱いやすく、衛生的です。大きな袋だと全部使い切るか、自分で小分けする手間がかかるので避けた方が◎。
実際におすすめしたい分け合える防災グッズ
ここからは、うちで備えてる“分けやすい”防災アイテムを紹介します。全部、自分が使ったり、結果的に相手に手渡して「助かった」と言われたり、本当に役に立ったと感じたものです。
① 長期保存水(500mlと2L両方)
- 500mlは持ち運びやすく、2Lは自宅用。
- 500mlを1本持っているだけでも、その人の半日分の命をつなげます。
② アルファ米(小分けタイプ)
- 1食ごとに包装されてるから、必要な分だけ渡せる。
- 水でもお湯でも作れるので、避難所でも安心。
③ モバイルバッテリー(2台持ち)
- 自分用と貸し出し用に分ける。
- 実際、家で集まっていたときに落雷で停電になったときに親戚にさっと貸したら「神!」って言われた(笑)
④ 簡易トイレ(個包装タイプ)
- 水が止まったときの必需品。
- 個包装なら衛生的で持ち運びもしやすい。
⑤ 衛生用品(マスク・ウェットティッシュ・手指消毒)
- 衛生品は「なくても死なないけど、あるとめちゃくちゃ助かる」系。
- 生理用品や尿漏れパッドは特に女性や子ども、高齢者には喜ばれます。下着を守れたり、状況に応じて使えるよう備えておくと安心。
分け合える備えが生む安心感
おじいちゃんが言ってた「最後まで、みんなで分け合わなあかんで」という言葉。昔はただの優しい言葉やと思ってたけど、今は“命を守る行動”やと感じます。
もちろん、自分と家族を守るのが第一。でも、ほんの少しの余裕があれば、誰かの命をつなぐことができるかもしれない。そんな力を持っているだけで、自分の心も落ち着きます。
近年は台風や大雨、地震など年々異常な天候が増えています。そんな自然災害の備えとして、
「分け合える備え」
はじめてみませんか?
English Summary
Emergency situations strike without warning, but preparation gives us peace of mind.
In this article, I share my grandfather’s wisdom on disaster readiness: from stocking daily essentials to ensuring the whole family can support one another.
It’s not just about survival—it’s about caring and staying connected, even in hard times.
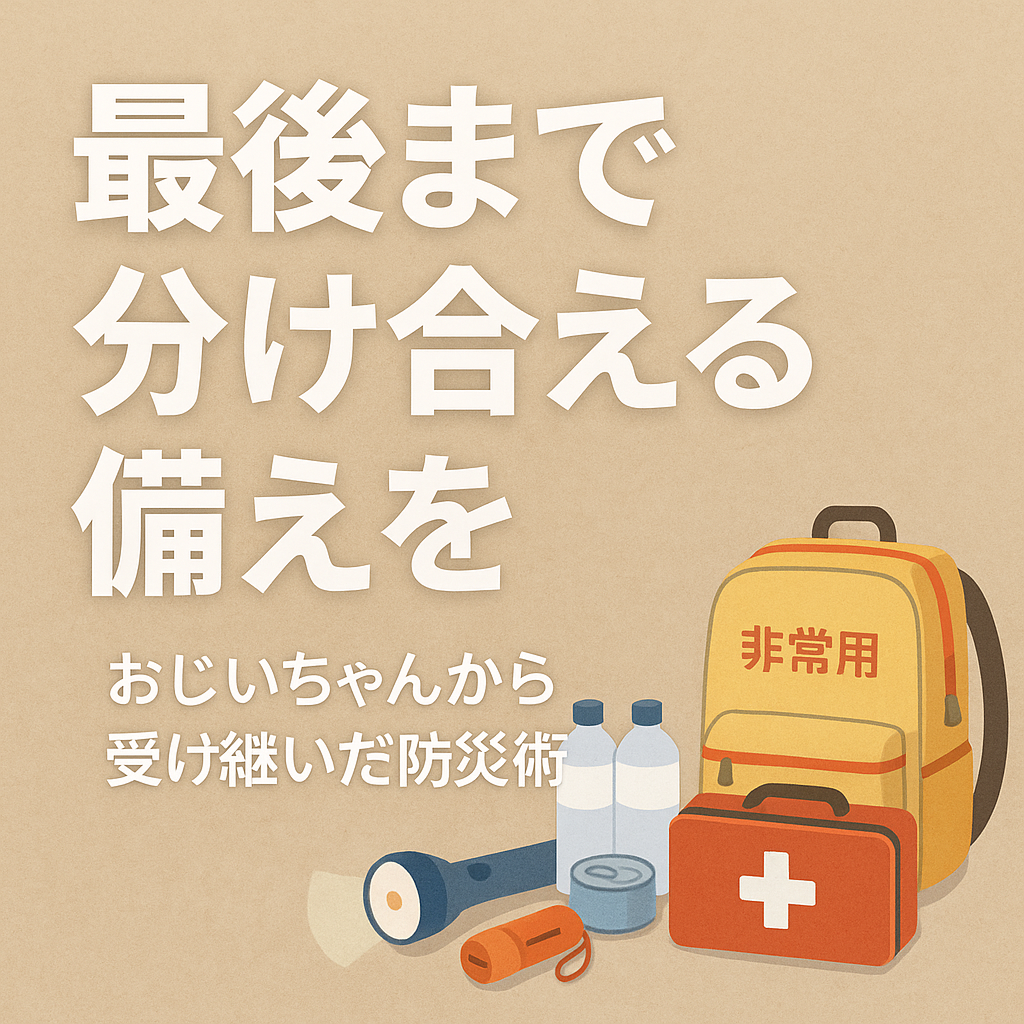


コメント